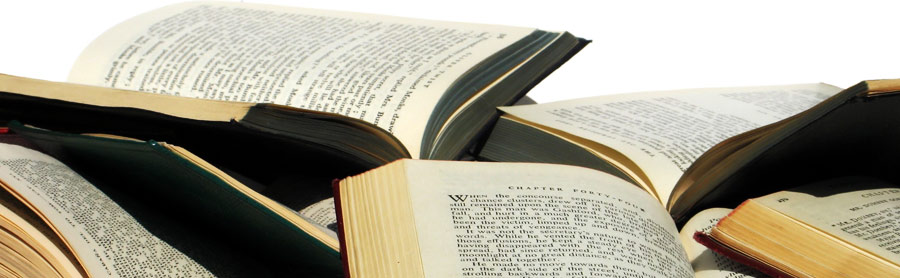教室の机の花束
教室の机の花束
おりーぶ。
1
シリア内戦により命を奪われたある小学生のことを私は覚えている。
彼女とその友人は、学校に通おうとしていた。
決して安全とは言えない中で、安心できずにその道を歩いていた。
朝の通学路。
突然鳴り響く銃声。
突然の叫び声。
一瞬のことだった。
彼女たちはその場で息絶えた。
誰にも気づかれずに、その場で倒れていた。
二人は手を繋いでいた。
解けないように、強く握られていた。
同級生の頬には微かに、伝った涙の跡が見えた。
安全な通学路も、教室と呼べるほどの設備も、何一つそろっていない空間。
日本の基準では、そこを「学校」と呼ぶことはできないだろう。
それでも、そこに通わなければ、何も学べないのだから。
翌日、彼女たちの悲報を聞いた同級生が静かに泣く声が、教室から聞こえた。
同級生の誰かが、道端に生えていた綺麗な花を摘み、机の上にそっと置いた。
衛生的な水が手に入らなかったため、その花は熱波の影響で刻々としぼんでいった。
このことを多くの日本人は知らないだろう。
なぜなら、日本ではほとんどといってよいほど、彼女たちのことが報じられないからだ。
そしてだれも見向きもせず、立ち止まりもせず、時の流れに洗われていく。
2
イギリス中部、マンチェスターで起きたテロ事件によって命を奪われたある小学生のことを私は覚えている。
そのテロ事件は、人気歌手のコンサート会場で起きた。
その歌手は、若者たちに人気だったという。
BBCをはじめとするメディアの情報は、日本でも伝えられた。
その容疑者が、事件直前に母親に一本の電話をかけていたという。
「許してほしい」と電話口で彼は言ったという。
もちろん、卑劣で残忍なテロ事件によって命を奪われた人たちは何も悪くない。
それでも、もし一瞬でもそう思う余裕があったなら、もしかしたらこの事件は止められていたかもしれない。
私にはそう思えて仕方ない。
8歳の少女は、このコンサートを訪れていた。
たまたま容疑者の近くにいたのだろう。
彼女の命は一瞬で奪われた。
とある誰かが、Twitterにそのことを投稿していた。
「彼女にはまだ未来があったはずなのに、こんな形で奪われてしまい、言葉にならない」
「コンサート会場に行った時には楽しみで仕方なかっただろう。悲しくて心が壊れそうだ」
彼女の悲報は世界中をあっという間に駆け巡った。
それは近年のインターネットなどの技術が支えた部分が大きいのだろう。
SNSでテロ事件のことや、その犠牲者のことが、瞬く間に拡散されていった。
彼女のことは新聞記事になり、それを見た日本人はもしかしたら覚えているかもしれない。
テレビでも報じられ、それをきっかけに彼女のことを知った人も多いだろう。
しかし、最近の若者は新聞を読まなくなった、という調査もあった。
それでも、明日になれば忘れているだろう。
やはり地理的な距離があるからか、対岸の火事だと思ってしまうのだろう。
画面の中の話だと思ってしまうのだろう。
彼女の悲報を知った同級生は、花屋に寄り、綺麗なバラの花束を買ってきた。
教師は花瓶を用意し、その花束を美しく飾った。
その花が枯れた時、静かに涙する同級生が何人もいた。
3
高齢者の運転により、命を奪われた日本人の小学生のことを私は覚えている。
彼のことは、新聞の一面に乗ったり、何回もテレビで報じられたりしたから、多くの日本人は覚えているだろう。
ネット上でも、さまざまな意見が投稿されていた。
高齢者の運転に否定的な意見。
その小学生へ向けられた悲しみ。
同じことが繰り返されてほしくないという思い。
彼の悲報を知った同級生は、机の上に花束を置いた。
現場近くには献花台が作られ、彼の遺影とともに、たくさんの花が置かれた。
その様子は、日本のテレビで、大きく報じられた。
その様子は、何日も、繰り返し、テレビや新聞で報じられた。
それを目にして、多くの人がそのことを忘れないでおこうと心に決め、そのような内容の投書も相次いだ。
ある程度時間が経っても、多くの日本人は覚えているかもしれない。
4
日本人に限ったことではないが、やはり多くの人は、外国で起きたことを対岸の火事としか思えないのだろう。
日本のニュースでも、国内のことが優先的に報じられる。
それはやはり報道の特性なのかもしれないが、そういう一面も生み出してしまっている。
海外で起きたこと。
地理的な距離が遠いことは私たちの努力でどうにもできない。
それでも、心理的に、少しでも近づこうと、寄り添おうとしてみたい。
国境を越えるのは物理的には難しいが、心理的には簡単だから。