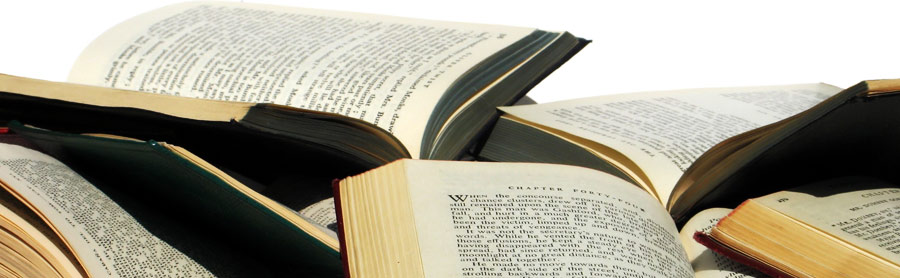ゆうひにとける
福江てん
何もすることがないのでただ長椅子に凭れ掛かって本を読んでいた。この家には若い女の娯楽といえるようなものは何一つなく、ただ厳めしくがらんとしているばかりだった。その癖本ばかりは十年かかっても読み切れないほどあってお化けのように壁中を埋め尽くしている。どの部屋もどの部屋も本棚のないところはなく、唯一の例外といえば女中の部屋と風呂場くらいのものだ。その上家の主人が偏屈なもので、上流階級の夫婦らしく今晩は芝居にでも連れ立って行こうなどというような洒落たことは一度も思いついた例がないのだった。いつも忙しくしている良人は毎日朝から晩まで外出しているので、自分と言葉を交わす暇すらないように見えた。口髭を蓄えて、父娘ほどにも歳の離れた頑固そうな良人を初めこそ恐れていたけれど、日々の会話が「いってらっしゃいませ」「云」「お帰りなさいませ」「云」だけでは殆ど他人様のようなものだと悟ってしまうのも時間の問題だった。
恨めしげな音を立ててドアーが開いて糊の効いた前掛けをした女が入って来た。「奥様水菓子をお上がりになりますか」小さな木の盆を持って、きっかり三歩向こうに立っている。とても物をたべるような心持ではない。要りませんから向こうへ行って頂戴と言いかけるとそれより先に女中が「まアこんなに暗いお部屋で御本なぞお読みなすって、御眼が悪うなりますよ」と言ってつかつかと文机に歩み寄り盆を置いた。どうするのかと見ていると今度は格子窓に歩み寄ってぴったりと閉じていたカアテンをさっと開けた。途端に西瓜を割った中身のような赤い光が窓枠のかたちに部屋に溢れ出る。まア綺麗な夕日だこと、御覧なさいませ奥様という女中のことばを聞くまでもなくやわらかい光に誘われるように窓の外を見た。細い雲がけぶるように甘くたなびき、ちょっとした西洋画のように見えた。
東京にもまだこんな空が残っていたのかと、自分は思わず本を膝に下ろして窓の外に見蕩れた。真っ赤に燃えたお天道様がまるで幾千の正義の矢を放っているような厳かな景色だ。窓から見下ろす町並みはその矢を受けて、すっかり清らかに生まれ変わっている。「まア」とやっとこさ口にした言葉は光に溶かされて消えた。常日頃汚い汚い、ぜんたい宅はどうしてこんなところに屋敷を建てたのか知らンと見おろしていた煤けた家々が生命を受けたように見えた。あの屋根一つ一つの下には人が暮らしているのだと、その実感が身体に夕陽と共に染み入った。思わず長椅子から立ち上がって窓辺による。窓枠にかけた自分の指も赤く赤く光っていた。
背後で聞きなれたキイという音がしたようだった。重い規則的な足音が近く聞こえた。
「いいところだろう」と陽光に照らされて良人が言った。
「ええ、」とだけそっと答えた。
明日は晴れるでしょうねと女中が言った。
Fin.